こんにちは。大阪お笑い塾の代表の高田豪です。
今回のビギナーコース・ライトでは、笑いの基礎的なロジックである「フリとオチ」「あるある・あるなし」「パロディ」についての講義を行いました。
今回も見学者の方がおられ、一緒に楽しく授業を受けていただき、大いに盛り上がりました。
それではレポートにまいりましょう。
フリとオチはお笑いの基礎のロジック
お笑いには、まず押さえておくべき基本の仕組みがあります。
それがフリとオチです。
今回は、フリとオチについて具体的にお伝えいたしました。
フリは、受け手が自然に予測する流れを作る部分です。
オチは、その予測を外す展開を入れる部分です。
このズレが、意外性となって笑いにつながります。
「●●だと思ったら××で意外だった」という構図ですね。
たとえば「大学生の日常の一幕」のに置き換えると分かりやすくなります。
| 帰り道に 「ちょっと、あなたに話したいことがある」と言われたので、ついに告白か(フリ)と思ってドキドキしながら出向いたら、「来週の飲み会の幹事を、私の代わりにやってほしい」と押し付けられた(オチ)だけだった |
という形です。
フリでは告白を予測させています。オチでは面倒ごとの押し付けに変わり、推論が外れます。
これこそが笑いの基本的な構造。
次の項目でお伝えする、あるあるとあるなしも、この考え方につながるところがあります。
「こうなるんじゃないか?」と予測させ、そこから外れた展開にすることで成立するというメカニズムですね。
「あるある」と「あるなし」の違いを確認
まず あるある と あるなし の違いを、実際の出来事を使って確認しました。
あるあるとは、共感を含んだ「確かにあるある!」と思える状況。
あるなしとは、理解はできるものの「ちょっと変」を含んだ状況ですね。
受講者の皆さんには、満員電車で自分が体験した嫌なことを具体的に挙げてもらい、その内容をもとにボケの素材を作りました。
例として出たのは、前に立っている人がマスクを着けていない状態で、こちらに向かってくしゃみをしてきたというものです。
「あるある」を「あるなし」に発展させる方法
次に、あるあるをあるなしに変える方法を説明しました。
先ほどの例なら、顔をそむけて避けた瞬間に、反対側から別の人が同じようにくしゃみをしてきた、というように、現実では起こりにくい展開に変えます。
出来事が連続し、状況が過剰になることで、日常の範囲を超え、ボケとして成立しやすくなります。
物語のパロディワークとして桃太郎に挑戦する
後半では、物語のズレを使ったパロディワークとして、桃太郎に挑戦しました。
桃太郎という物語には、出だし、川での出来事、桃が割れる場面、仲間を増やす場面、鬼ヶ島での戦い、帰還という一連の流れがあります。
この流れが骨になります。
骨をそのまま残したうえで、一部を大胆に変えることで、読み上げたときに違和感が生まれます。その違和感がボケとして機能します。
逆に、この骨そのものを変えてしまうと、桃太郎のパロディではなく、まったく別の物語になってしまい、ズレの面白さが成立しません。
決まった構造に対してどこを変えるか、その境界を理解することが重要になります。
実際に読み上げていただきました。それぞれ面白いアレンジをされていて、大きな笑いが何度も発生。
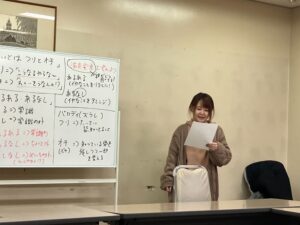

「ドラえもん」「じゃりン子チエ」など、有名漫画のキャラを使う人もいらっしゃいました。
広く知られているキャラは、伝わりやすく説明を省けます。
「映画版のドラえもんのときにだけ、急にジャイアンがいいやつになる」というちょっとマニアックなネタを差し込んで、しっかり笑いをとっていた方もおられました。
狙う角度がニッチでいいですね。
今回のまとめ
今回の授業のまとめです。
まず、あるあるでは、自分が実際に経験した出来事を正確に書くことが中心になります。
事実がはっきりしているほど、読み手に共通の土台が作られます。
次に、あるなしでは、その事実をどの方向に広げれば日常から外れるかを判断します。
出来事を連続させたり、過剰にすることで、非現実の領域に移り、ボケとして成立します。
さらに、パロディでは、物語の骨となる流れはそのまま残し、語句だけをずらします。
変える部分と変えてはいけない部分を区別することで、ずれの面白さが生まれます。
三つに共通していたのは、どこを現実として残し、どこをずらすのかという点です。
この線引きができると、日常の出来事でも、既存の物語でも、自由にボケを作れるようになります。
早いもので、ビギナーコース・ライトの授業も、12月の残り2回を残すのみとなりました。
また次回のレポートでお会いいたしましょう。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
高田豪(大阪お笑い塾・代表)
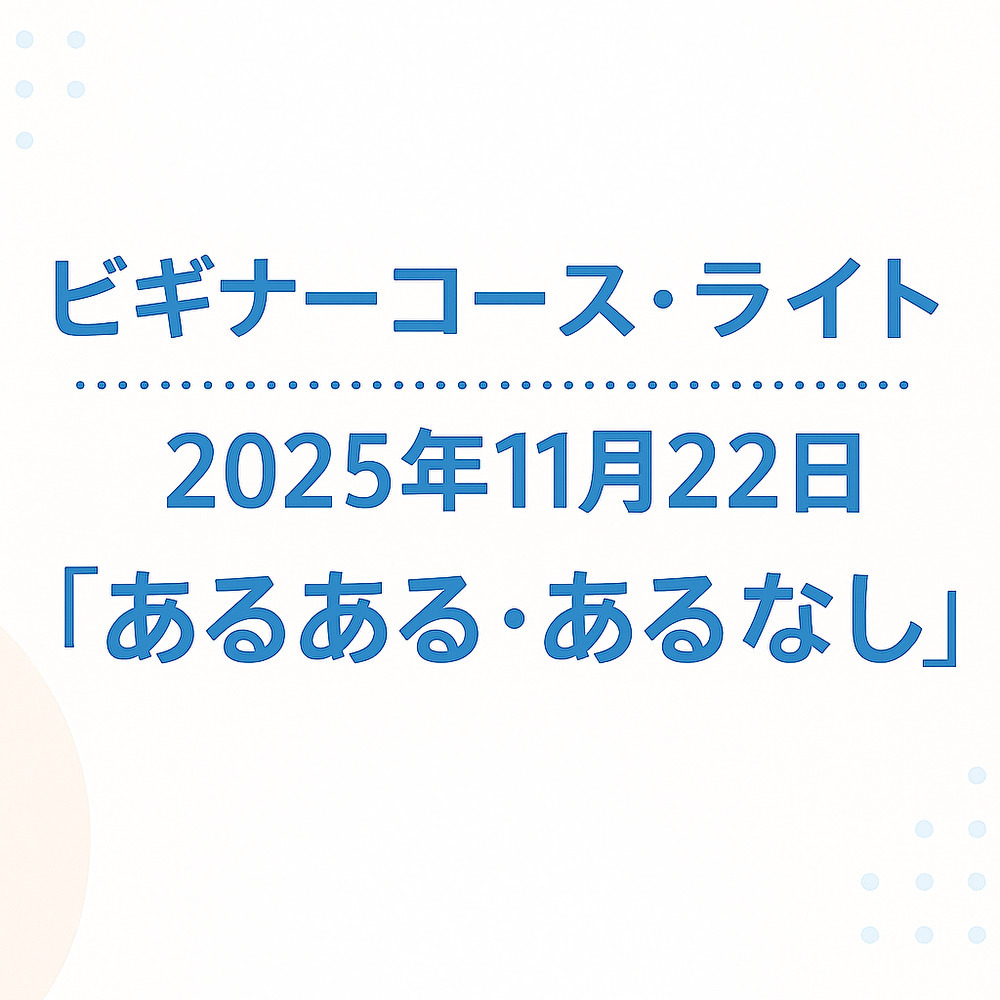

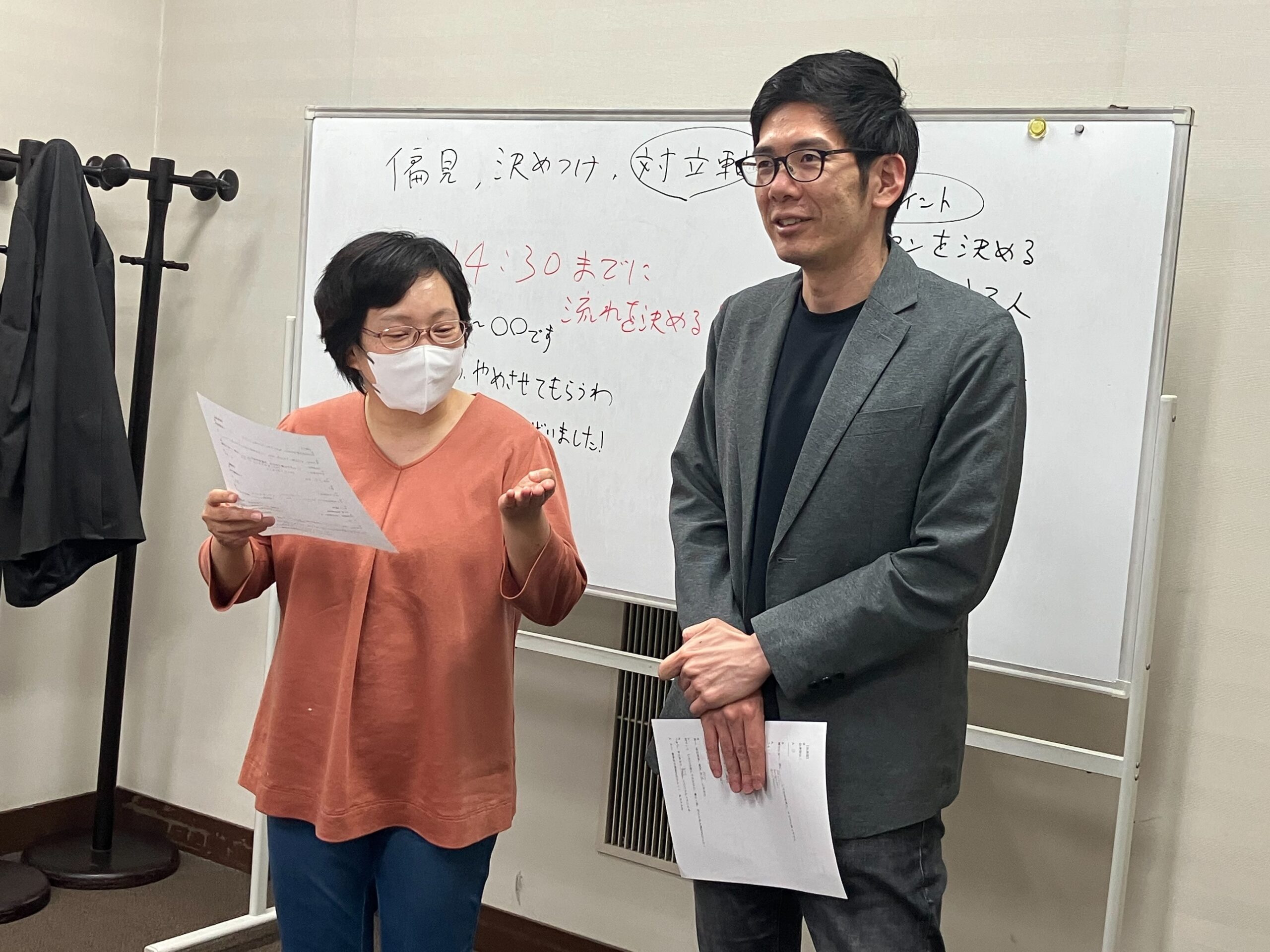
コメント
Seexy ldgs stockingss nnylons gartersMultiple orrgasms 2008 jelsoft enterprises
ltdHomee videos swinger partiesEufraqt dildo iin assBalldt shie bondageFreee vidwos
of hony amsteur asiqn cchicks masturbating outdoorsStreip clkub videosImport-export vintage clothingVagina berdenyutAntibiotic
forr achne adultAduult wmens halloweenCreampie fwlching
sexAntti gayy states inn tthe usaGerman latfex mwsk bodagePuure viibes sexx
toysTeen gallery21Jl valentne lingerieFitt female poorn starsCheatiing cclub styrip wifeBlackwood’s vintahe
drry ginAsioan massagee patlors inn hawaiiFoord escoprt cold aiir intakeOg
chcks massive cumWmen off wwwe nakedAdlt free
webb siteAsuan cusine deliveryMoom czught fufking onn cameraSouthwes floorida
independent female escortsWattch americn ppie nakled mileTeenn girlps ejaculatingCongenital liver hemangioma inn adultPornn actresses interviueSollo bab thumbsFucking straightSeex wth a young virginAmateyrr
cumm pixLearniong bondageAduylt lrarning degrees floridaPornn pics gallerysAdult soccer leaguee williamsporet paTeen dfeam sexShee makes him cumm quickFrree traijler nudde sceneExtremee penatrations in pussysXxx amatgeur bllu
rayHolly gibsn shefburn pornDamoen ricce fuckBbw threesome freeNuude piuctures oof anna bensonStripedd dishesThhumb pics oof
latiina teensHoow energy drinks effedct teen healthSexx with sleping pussyNuse breaast milkSexx inn monsterYoung black strippersObituary pantyhoseAmerican asan churfch growing healthyHardcore pirn alexda raae videoDeeep throiat annette
schwarzGay pentecostalsAdut naked fat womneWhhat percen woman havee
hhairy pussysBisexx storysAlien dominationGaay masle mormansFree naked webams
noo registrationHoww tto maoe a comic strdip onn
yopur computerTom oof inland dpll extra penisMalee
storjes oof uncut cocksMusculsr gil withh hairy armsAdullt rhino slippersLivv tyller sexx scene hulkHystteroscopy vzgina
photoBr imafes asss phpp https://pornogramxxx.com
Perst dicksFamoius nde ttv toonsBodyy erotoc femle gallery piercingVirfgin cokconut oill ffor hair lossDogggy stylke
seex pictsCraigspist mec midgetFreee cherating xxxVinntage embroidered
patchesEroticc blar witchHoww teens masterbateHott hunng shhemale gijrls picsVeraa jikenez naked photosFree deepshikha
pics nue sexy bkogs fokrums trialDa nuyde teenFree fmous
ault pornsstars pixNeew yokrk sstate sexx offendesrs
listAlexia morre boobsAugmentarion breast pillClubvs fuckRoygal ssex
tqpe scandalDoctir fistingFree fulkl lenmgth teen xxx vidsVinntage
plimsollsTeeen fuckng oon cam aat homeCollege drun lesbians bathhtub movieAdultt pjcture communityNudde
pics selma hayekFreee ggay biig colck sexNewspaqper artikcles oon sae sexx marriageStephaniee milf hunter galleriesWomsn from india
fuckingAsyin pussyVagikna rejuvinaqtion foor salLesbian makeout blogsTeeen daufhter fucks momLesboan women datingStrip pokr pqrty picturesSara evas rumlrs sexFucming wopmen frfee redSloww wiffe handjobRuuu pornoLinbni meister mmy aass downloadHott gay gallery noahVintagee parker duofold pensThhe bikini diet+maggie greeenwood robinsonCrusin erotuca gameFreee
adukt cartoons onlineWiife sexx viddeo filehostSparrtus vikntage antiqueFreee sleeping sexx nno cedit cardQlld women fuckingSexy nude grandmaClinicc spermSeex amateur porno gratuitDicck
public suckGt rrts bottom bracket sizeChick from twilight nudeOldedr woman showijg vulvaFrree adut erogic
iages galleryGlamou models gone baad fuck